■概要
Airtableで管理しているタスクやバグ報告を、手作業でGitHubにIssueとして起票していませんか?この作業は単純ですが時間がかかり、コピー&ペーストのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtableにレコードを登録するだけで、承認フローを経てGitHubに自動でIssueを作成できます。AirtableとGitHubを連携させることで、こうした面倒な手作業から解放され、よりスムーズなプロジェクト進行を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
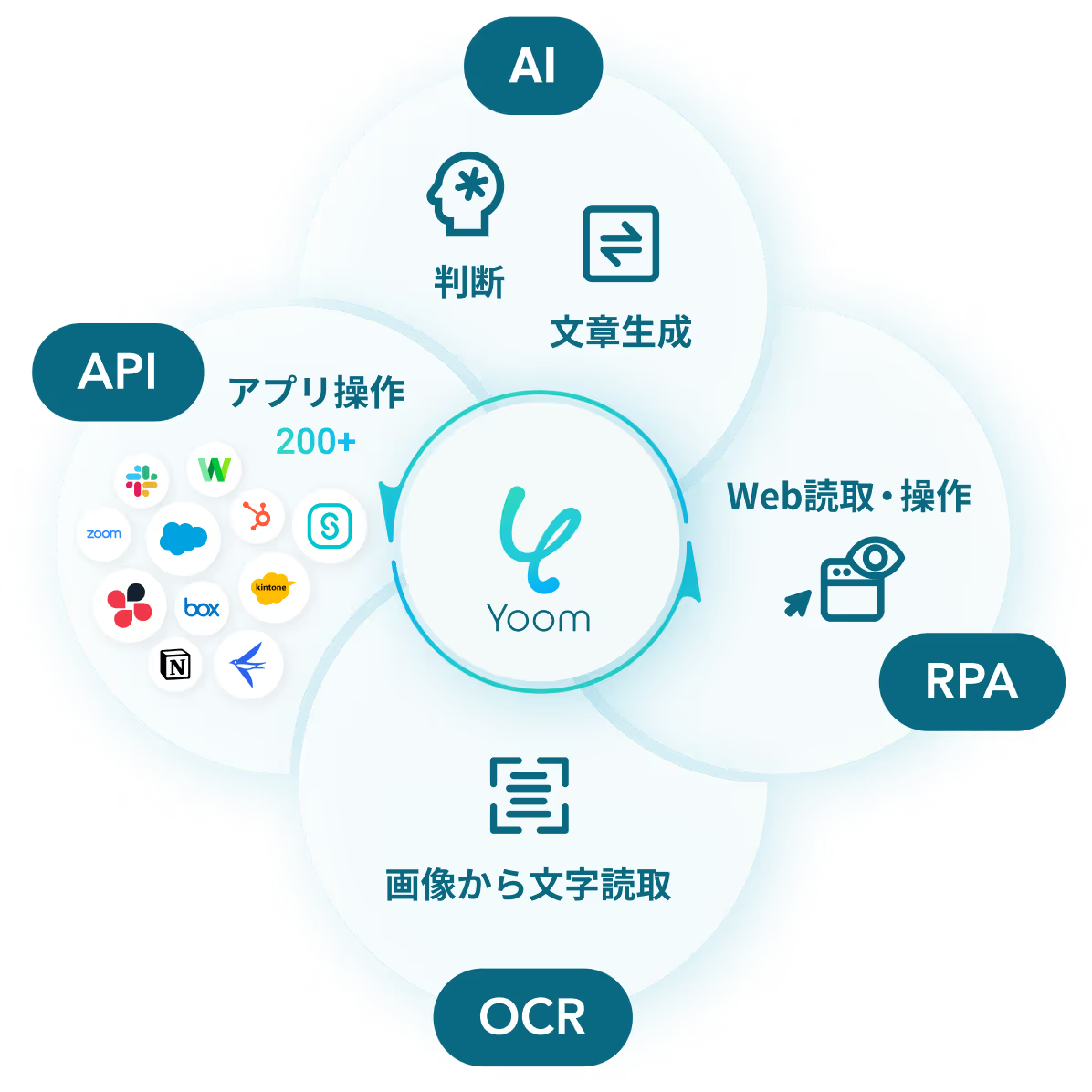


 レコードが登録されたら
レコードが登録されたら
 レコードが更新されたら
レコードが更新されたら
 Issueが新しく作成されたら
Issueが新しく作成されたら
 Issueが新しく作成または更新されたら
Issueが新しく作成または更新されたら
 プルリクエストが作成されたら
プルリクエストが作成されたら
 プルリクエストが作成または更新されたら
プルリクエストが作成または更新されたら
 IssueまたはPull Requestにコメントが作成されたら
IssueまたはPull Requestにコメントが作成されたら
 Issueがクローズされたら(Webhook起動)
Issueがクローズされたら(Webhook起動)
 Issueがオープンされたら(Webhook起動)
Issueがオープンされたら(Webhook起動)
 Webhookを受信したら(Webhook起動)
Webhookを受信したら(Webhook起動)
 Pull Requestがマージされたら(Webhook起動)
Pull Requestがマージされたら(Webhook起動)
 レコードを取得
レコードを取得
 レコードを作成
レコードを作成
 レコードを更新
レコードを更新
 レコードを削除
レコードを削除
 レコードにファイルを添付
レコードにファイルを添付
 コメントを作成
コメントを作成
 レコードを検索する(キーワード検索)
レコードを検索する(キーワード検索)
 レコードの一覧を取得する
レコードの一覧を取得する
 レコードのファイルをダウンロード
レコードのファイルをダウンロード
 Issueを作成
Issueを作成
 リポジトリにユーザーを追加する
リポジトリにユーザーを追加する
 Issueの一覧を取得
Issueの一覧を取得
 Issueを取得
Issueを取得
 Issue・Pull Requestにコメントを追加
Issue・Pull Requestにコメントを追加
 Issueを更新
Issueを更新
 IssueとPull Requestを検索
IssueとPull Requestを検索
 ユーザーを検索
ユーザーを検索
 プルリクエストを作成
プルリクエストを作成
 レコードが登録されたら
レコードが登録されたら レコードが更新されたら
レコードが更新されたら レコードを取得
レコードを取得 レコードを作成
レコードを作成 レコードを更新
レコードを更新 レコードを削除
レコードを削除 レコードにファイルを添付
レコードにファイルを添付 コメントを作成
コメントを作成 レコードを検索する(キーワード検索)
レコードを検索する(キーワード検索) レコードの一覧を取得する
レコードの一覧を取得する レコードのファイルをダウンロード
レコードのファイルをダウンロード Issueが新しく作成されたら
Issueが新しく作成されたら Issueが新しく作成または更新されたら
Issueが新しく作成または更新されたら プルリクエストが作成されたら
プルリクエストが作成されたら プルリクエストが作成または更新されたら
プルリクエストが作成または更新されたら IssueまたはPull Requestにコメントが作成されたら
IssueまたはPull Requestにコメントが作成されたら Issueがクローズされたら(Webhook起動)
Issueがクローズされたら(Webhook起動) Issueがオープンされたら(Webhook起動)
Issueがオープンされたら(Webhook起動) Webhookを受信したら(Webhook起動)
Webhookを受信したら(Webhook起動) Pull Requestがマージされたら(Webhook起動)
Pull Requestがマージされたら(Webhook起動) Issueを作成
Issueを作成 リポジトリにユーザーを追加する
リポジトリにユーザーを追加する Issueの一覧を取得
Issueの一覧を取得 Issueを取得
Issueを取得 Issue・Pull Requestにコメントを追加
Issue・Pull Requestにコメントを追加 Issueを更新
Issueを更新 IssueとPull Requestを検索
IssueとPull Requestを検索 ユーザーを検索
ユーザーを検索 プルリクエストを作成
プルリクエストを作成 プルリクエストを取得
プルリクエストを取得 プルリクエストを更新
プルリクエストを更新 リポジトリからユーザーを削除
リポジトリからユーザーを削除 Issueを検索
Issueを検索 Pull Requestを検索
Pull Requestを検索 コミットの一覧を取得する
コミットの一覧を取得する リリースノートを作成する
リリースノートを作成する